新学期になり1週間以上経過した。元不登校娘も高校2年生のスタートがまずまずでホッとしている。新学期初日は、果たして行けるのか?やはり行けないのか?と、学校に行けている今でも不安になる。思考のくせなのか、もうこの子は大丈夫だと思っていても、やっぱり心のどこかに、行ける行けないの期待と不安があるのだと思う。私ってまだまだ未熟だなってつくづく思い知らされる。そして、やっぱり学校には行ってほしいと思っているんだなと再認識する。
さて、小学校時代は保健室登校の時期があった娘。中学校は保健室登校ではなく、別室登校という形を経験した。入学当初から、行き渋りがたまにあった中1時代。時々休みながら、教室に普通に登校する1年を終えた。担任の先生の理解があり、休むことで元気になるのなら良かった、と言ってくださる先生で、人見知りのはげしい娘も、この先生のことは真っ先に信頼のおける先生だと認識したようだ。中2の二学期後半になってくると、徐々に休みが増え、別室を利用することが増えてきた。中3になるとほぼ教室にも行けず、別室または休むということがほとんどになっていた。別室登校の子は何をして過ごすのかと言うと、リモートで授業を聞く、自主学習をする、読書をする、といった感じ。リモート授業と言っても、リモート向けの授業ではないので、分かりにくいそうだ。画質も良くないし、ピントもずれていたり、声が途絶えたりと道半ば。自主学習は本気の自主学習。自前で学習教材を用意し、分からなくても聞ける人はいない。当然理解すべき授業内容には到底ほど遠い。たまに授業内容に沿った教材を用意してくれる先生もいる。誰か1人先生が交代でいるのだが、基本いるだけ、見守り。共通していえるのは、どんなにリモートでつないで授業を聞いても、どんなに頑張って自主学習や課題をこなしても、ほぼ評価にはつながらないということ。出席日数だけは反映されるという仕組み。本来は評価につながる材料を学校が用意し、積極的に評価しなければならないと国は言っているのだけど、それを知らない先生は本当に多いし、知っていても余裕がないのだと思う。たまに授業内容に沿った教材を用意してくださる先生は、不登校支援に理解があるのか、忙しい中、子供たちがこなした内容を極力評価につなげてくれる。この別室登校をしている子への評価の仕方が先生により本当に様々で、その違いに驚いたのだけど、それはまた改めて。
別室でもいいから登校することで安心するのは一体誰なのか?紛れもなく大人である。先生もだし保護者も。子供たちは学校行きたくないって言っているのだから、きっと別室登校は大人から言われて渋々行く場合がほとんどではなかろうか。もちろん出席日数としてカウントはされるので、欠席するよりは良いという面もあるとは思う。教室には行けなかったけど学校には頑張って行ったという事実が、周りからの評価、例えば高校受験において、マイナスに働くことはない。我が家の場合も、お願いだから別室でもいいから行ってほしいと親は思っていた。本人も別室なら行けるかも、と、それでも苦しい思いをしながら何とか登校していたと思う。学校には何とか行けているというほんの少しの安心感、あわよくば教室に行けるのではないかという淡い期待。本当に親って勝手である。このまま学校に行けなくなる→高校も行けない→就職なんてあるわけない→引きこもりという極端な思考に陥ってしまうほど、スムーズでない子供の登校は、親をも追い詰めてしまう。皆が皆そうではないけど、私はそうだった。親も子も苦しい日々。それでも学校に行かせなければ、行かなければ、の縛り思考。苦しい思いをしてまで行っている別室。最初は別室でも良い、とにかく行ければ良い、そのうち教室に戻れば良い、と思っていても、次第に生まれる疑問。別室登校が当たり前になってくると、日々成長するであろうこの貴重な中学生時代を、別室で長時間過ごすことに費やして良いのだろうか?狭い空間で数人の仲間と日替わりの先生の中で、身の入らない自主学習をし続ける意味は?この大事な日々を、学校から大切にされていないと感じながら過ごすむなしさと無意味さ。娘にとって、プラス面がない、時間がもったいない、と遅ればせながら私は気づいた。良く気がけてくれる先生と、同じ境遇で理解し合える仲間には感謝しつつも、とにかくこのままでは良くないと考えた我が家は、フリースクールへ通うこととした。学校としては別室でもいいから登校してほしい、というスタンスなのかもしれない。でも、もう別室に行くことの意味も見いだせないのは親だけでなく、娘自身も感じていたようで、親子で迷いはなかった。学校のために登校するわけじゃない、担任のために登校するわけじゃない、娘と娘がこれから歩む人生のための大きな方向転換。遅かったかもしれないけど、この決断は間違いではなかったことは、常にいつも今が答え。進んだ道を正解にする、と言って今春旅立った息子のように、選んだ道を正解にすれば良いんだとつくづく思う。

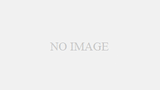
コメント