新学期が始まった。我が家の子供たちも、それぞれ進学、進級と新しい環境で過ごしている。特に上の長男くん。晴れて大学生となり、念願の1人暮らし開始。第一志望校ではないけど、進んだ道を正解にする、と頼もしい言葉を残して旅立った。この長男くんに関しては、学校に行きたくないなど一度も言ったことがなく、集団にもすぐ馴染み、友達も多い方で、学校や友達に関する問題は一度もなくここまで来ている。今も新しいことだらけで戸惑うことも多いだろうけど、楽しそうにしている。ホッとした。一方、小中学校と登校がスムーズでなかった下の娘。無事に高校2年生に進級した。中学校後半はほとんど登校できなかった娘だけど、本人の希望で、全日制の公立高校受験にチャレンジ。めでたく合格し、不安定な時期もありながら一年生を終えた。本人の努力、周りの支えあってこそ。
新しい年度が始まり、新しい学校、新しい学年、新しい先生、新しい教室、新しいクラスメイト。楽しくて仕方ない子も不安で不安で仕方ない子も、スムーズに馴染めた子もそうでない子もいるだろう。来週後半あたりになると、どんな子も少し疲れが見えてくる頃かな?そしてGW。このGW前後が、学校に行きづらい子の最初の山場ではなかろうか。それまでどうにか頑張って登校してた子が息切れし始めるのがこの頃だと、私は経験上思っている。
高校2年生になった娘。保健室登校や別室登校を小中学校時代何度も経験してきた。教室に行けていた時期もあるし、登校さえできなかった時期もある。小学校時代は別室登校という環境がなく、保健室で過ごさせてもらった時期がある。保健室に一日中いるわけではなく、教室がきつくなったら保健室へ行く、という感じだった。または登校後保健室でワンクッション置いたのち教室へ行くといった具合。ただ保健室の居心地は養護の先生によってガラッと変わる。何人もの養護の先生に出会ったけど、居心地がいいからずっと居座る、のではなく、困ったらここに来ても良いのだという安心感で子供たちは教室で頑張っているように私は感じた。「ここは病気の人が来るところです。教室へ入れない人が来るところではありません。」と仰った先生の時は、「〇〇さんが教室に行きたいって言ってたので連れてきました。」と言って娘を無理矢理教室に戻す、ということが行われていたそう。保健室どころか学校からも足が遠のいた。打って変わって、「私が一旦預かります。大丈夫ですよ。ここにずっと居続けることにはならないですよ。」と仰る先生もいた。この先生の時は娘は元気の過ごすようになり、教室で頑張る時間が増えた。保健室に全く行かなくなるくらいに。昼休みにこっそり娘が一人で保健室に遊びに来るという話を後々聞いた。後者の先生の方が良いのだけど、それぞれ考えがあってのこと。教室に行けない子を預かるのは私の仕事ではない、と考える先生がいても仕方ない。心の疲れは目に見えない。体の調子が良くない時に保健室を利用するのと同じように、心の調子が良くない時に保健室に来ても良いと考える先生もいて、私たち親子にはありがたい、心の支え的な存在となる。
保健室登校が良いのか悪いのかは分からない。保健室登校と言っても、一日中保健室で過ごす子はあまりいないのではないかと思う。保健室とはいえ学校なのだから。そもそも教室に行けない子が長時間滞在する場所ではない。ただやっぱり教室にスムーズに行けない子の一時的な避難場所、心のよりどころのひとつであって欲しいとは思う。保健室でもいい、短時間でもいい、学校に行けたとう安心感が親に生まれるのは事実。子供自身の本心は分からない。学校に全然行かないよりはいい、という親の自己満足なのかもしれないね。
娘の場合、保健室、養護の先生の存在が大きく、小学校時代に完全不登校になることはなかった。本人は学校は苦手だけど、行きたくはないけどやっぱり行きたい、という感じだった。だからこそ保健室のありがたみはものすごく感じた小学校時代だった。中学校に上がると最初は普通に登校できていた娘。のちに別室登校という形を経験するのだけど、こちらに関しては色々思うことがあったので、また別に綴ろうと思う。

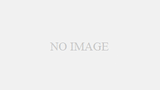
コメント