この春、小学校や中学校に入学した知り合いの一年生たちも、徐々に不安が和らいで、登校がスムーズになったという話を耳にする。特に小学校に入学した一人の子は、連日行きたくない、保育園に戻りたいと泣いてばかりで、下にも小さい子が二人いて、親もとても大変そうだった。学校生活が分からないことばかりで不安で行きたくないということももちろんあったけど、話を聞く限り、朝、お母さんと離れる瞬間がさみしい印象だった。その子も今週はやっと朝から一人で家を出て登校班で行けるようになったと。焦らず寄り添って、不安を取り除いてきた日々だったのだろうなと思う。親子で頑張ってひとつ山を乗り越えたんだなと。進級した子たちも新しい環境で頑張ってるね。慣れるペースは本当にその子その子で違うから、まだまだの子もいるかもしれないし、行きつ戻りつ前に進むんだと思う。
小中学校時代に不登校を経験した娘も全日制の高校二年生、なんと新学期はまだ一日も休まず頑張れているではないか。聴覚過敏や発達特性もあり、すごく疲れて帰宅する日がほとんどだけど、自分で折り合いをつけて、頑張っているのだと思う。休む、とは言わなくなった。昨年度は時々休み、睡眠がとれなくなったり、鬱々したり、もうこの学校に通うのは無理かもしれないという時期があった。特にこれという原因があったわけではないけど、行事ごと盛りだくさんの二学期は、行事ごとが苦手な娘にはハードすぎた。一部の授業での困りごとも発覚し、何とか日々をこなしてはいたけど、知らず知らずのうちにきつくなっていったのではないかと思う。特性あり、不登校経験ありの娘にとって、全日制高校への入学はハードルの高いものだとは分かっていた、けれど、学びたい気持ちがあり、チャレンジした。やれるだけやってみたい娘の気持ちを大事にした。3学期は短くあっという間、登校渋りもなく、無事に進級した娘は、今の学校を卒業し、就職するという未来を思い描いている。
娘の登校が不安定になった昨年度の一時期、担任の先生とのやりとりも何度かあった。よく話を聞いてくださる先生で、発達障害の子への理解を深めようとしてくださる姿勢が、今までの担任の先生の中では一番だと私は感じている。教育センターや中学校時代にお世話になったフリースクールの先生にも話を聞いてもらい、娘の不安定な時期、私自身気持ちを落ち着けてきた。娘には発達の特性に関することで、学校では一部配慮いただいている。個別の支援に関して、もう少し具体的なお願いを学校にしても良いという教育センターとフリースクールの先生との共通のアドバイスがあったので、タイミングをみて学校側に伝えた。行事ごとのない学校に行けばいい、個別指導をしてくれる学校に行けばいい、そんな声が聞こえてきそうだけど、こちらにも学ぶ権利はある。相手側の可能な範囲で、足りない部分は力を貸していただきながら、こちらはこちらで努力するというスタンスを私は貫いてきた。娘にも、皆と同じやり方ができなくても色々な方法があるのだとずっと伝えてきた。学校側に支援をお願いするときは必ず、こちらでできる具体的な努力とセットでお伝えするのが大事かなと思う。面倒くさい親かもしれんし、他の学校行けよって思われるかもしれん。けど、そんなことしたら、多様性を認めようとかいう世の中の風潮と矛盾する。時と場合、障害の程度によっては、専門の場所が安心な場合があるから、一概には言えんっては思う。
娘は高校卒業後は就職を希望していて、必然的に就職のことを考える機会が多い環境にあるのだけど、将来の自分の姿や就職先や職種について具体的に思い描いている。希望をもっていることが嬉しい。発達の特性ありだけど、先生方からしても私からしても、今のところ普通に就職で大丈夫そう。心配は、仕事ができないのではないかということではなく、過剰適応するため、精神のバランスを崩すのではないかということ。娘には社会に出るまでの二年間で、自分の得手不得手をより把握して、生きていく上でのスキルをたくさん習得してもらいたいと思っている。自立とは、何でもかんでも自分一人でできるようになることではなく、できないことは力を貸してほしいと人に言えることだと、中学校の卒業式での育友会長さんの言葉が思い出される。
先日ひとつうれしいことがあった。聴覚過敏に関して、きついときは校内で耳栓やイヤホンを使わせて欲しいことを、自ら担任の先生に相談に行ったと、娘が話してくれたのだ。人の声はちゃんと聞こえること、イヤホンと言っても音楽を聴ける状態にはならないこと、他先生と色々確認し、許可されたとのこと。私は一切関わらなかった。そんな日がくるなんてまだ先のことだと思っていたから、驚いた。実際に耳栓やイヤホンを学校生活の中で使うことは、経験上そんなにないとは思う。けれど、この一連の娘の行動には成長を感じた。登校渋りや不登校の苦しい時期からは想像もできなかった未来を今、娘も私も生きている。

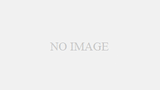
コメント